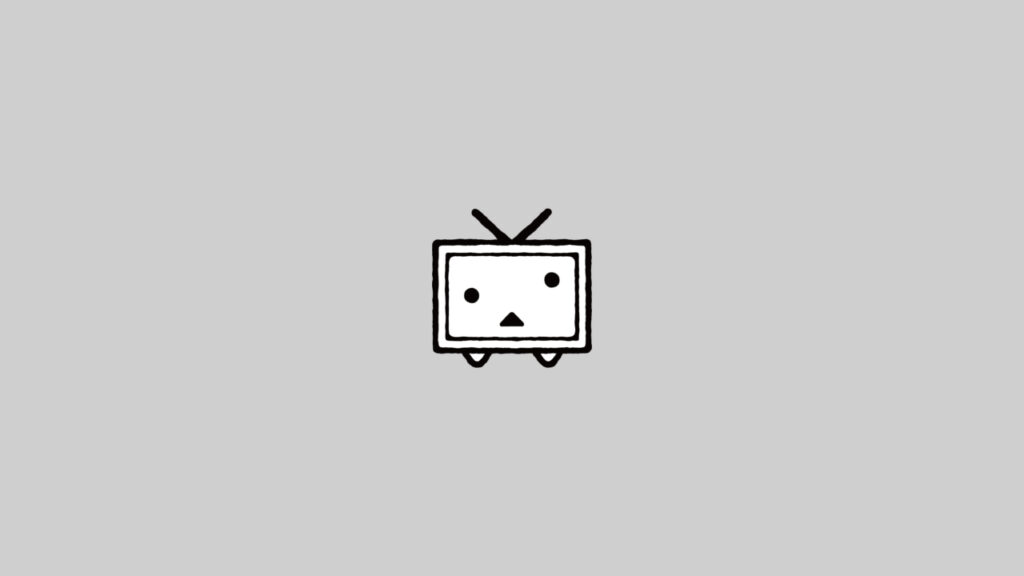歌ってみたMIX、
ボーカルトラックに
コンプレッサーをかける
ところから始まると思います。
人によって言ってることが違いすぎて
「けっきょく、コンプってどんな風に使えばいいんだ…?」
お困りのこととお察しします。
MIX素材としてのボーカルには
ほんとにいろんな形があって
- ダイナミクスが大きいボーカル
- ダイナミクスが小さいボーカル
この他にも
ボーカルトラックの性質は
述べ9000種類にも分かれていると言われていて(事実無根)
要するに、ほんとに多種多様です。
歌ってみたMIXを
10年以上やってきた僕の場合ですが
一貫して
『コンプレッサーの多段がけ』
を実践してますし、推奨してます。
ボーカルはダイナミクスが揺れやすい素材
大前提として、
ボーカルはダイナミクスが揺れやすい素材です。
「あぁ~………」と発声するのと
「「「ァアーーー!!!」」」と発声するのとでは
聴こえ方がぜんぜん違いますよね。
聴こえ方が違うということは
録れ音にも影響するということです。
プロだから音量がまとまってるとか、
素人だから音量がバラバラだとか、
そういう問題じゃないんです。
素材が人間の声である以上、
ダイナミクスはどうしても生まれるのです。
ので、
コンプレッサーは
慎重に設定していきましょう~
1パターンのコンプレッサー設定だと矛盾しやすい
音量差が大きいボーカルの場合、
コンプレッサー1つだと不自然になりがちです。
正確には、
1パターンの設定で
ボーカル全体を均一化しようとすると矛盾が生じる
んですね。
コンプレッサーの設定を
大きいところに合わせると
→小さいところにちっとも作用しない
小さいところに合わせると
→大きいところがペショペショになって聴けたモンじゃない
ということが起きがちです。
なので必然的に
『多段がけ』
が一番コスパよくまとめやすいな~
という結論でございます。
ボーカルコンプレッサーの多段がけ設定
順番やコンプレッサー設定は
素材によって変えていきますが、
基本的に
- 1段目:アタックを削り取る
- 2段目:ボディをならす
- (3段目:全体をもう一度なめらかにならす)
こんなプロセス。
3段目に()が付いてるのは、
3段目のコンプをかけるかどうか?は
ケースバイケースで
やる・やらないを判断するからです。
1段目のコンプレッサー設定

1段目のコンプレッサー設定は
- レシオ:8 or 12
- アタック:1
- リリース:7
- GR(INPUT):通常部分で-1~2dB・サビなど大きい部分で-3dB前後
- OUTPUT:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量
僕はこんな設定にしてます。
ちなみにレシオが高いのは
僕の場合、
CLA-76の工程で
ボーカルの音圧感まで作るからです。
(CLA-76の、レシオ上げると全体がグワッと持ち上がるのを利用)
これは歌ってみた特有の
音作りテクでしょうから、
好みに合わせて調整してください。
もし
CLA-76を持ってない場合は
お持ちのコンプレッサーで代替して
- レシオ:深め
- アタック:ベリー早め~早め
- リリース:早め~ちょい早め
- スレッショルド:通常部分で-1~2dB・サビなど大きい部分で-3dB前後
こんな設定がいいでしょう。
1段目のコンプはとにかく
- 耳に刺さるアタックを叩く!!!
- 他の部分に作用してなくても気にしない
ということを意識してみてください。
2段目のコンプレッサー設定
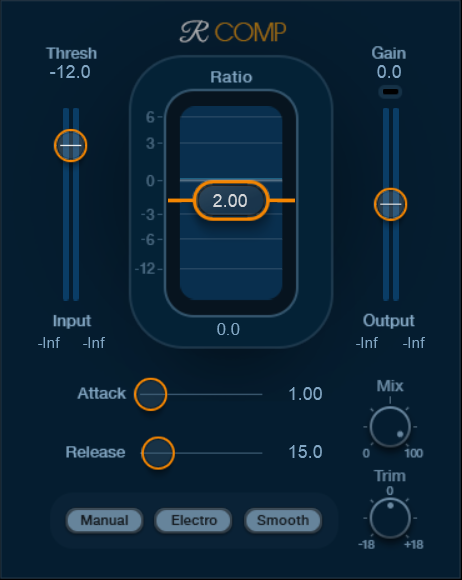
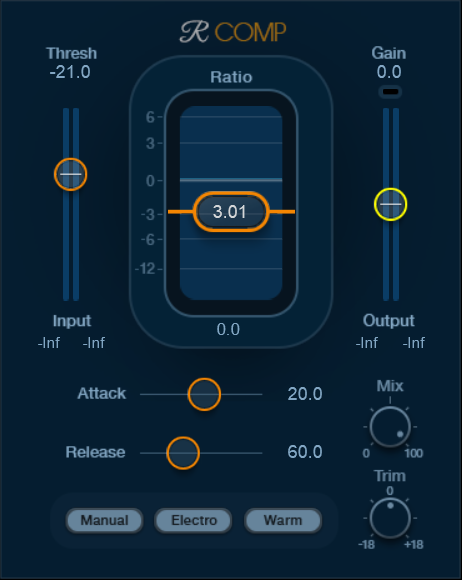
2段目のコンプレッサー設定は
- レシオ:2
- アタック:1ms
- リリース:15ms
- スレッショルド:GR-1~2dB
- OUTPUT:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量
- Manual・Electro・Smooth
と、
- レシオ:3
- アタック:20ms
- リリース:45~60msで調整
- GR(INPUT):-4~5dB
- OUTPUT:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量
- Manual・Electro・Warm
僕はこんな設定にしてます。
「2段目っつっといて2つ使っとるやん」
返す言葉もございません…
でもこれがいい音になるのです…
クレメンス…(謝罪を略すな)
Renaissance Compressorの
デジタル臭さで
- ぴったり
- べったり
- タイトに仕上げる
ことを意識してます。
(歌ってみたの場合、2MIXオケに馴染みやすくするため)
もし
Renaissance Compressorを持ってない場合は
お持ちのコンプレッサーで代替して
- レシオ:2~3
- アタック:早め~ちょい早め
- リリース:ちょい早め~並
- スレッショルド:GR前段-1~2dB・後段-4~5dB
こんな設定がいいでしょう。
3段目のコンプレッサー設定
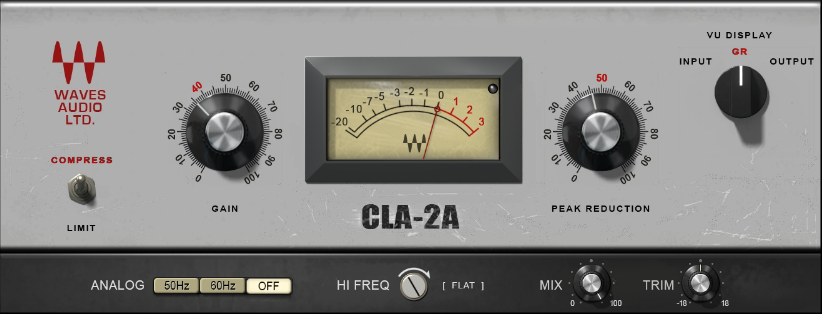
3段目のコンプレッサー設定は
- GAIN:バイパスと聴き比べて同じくらいの音量
- PEAK REDUCTION:-1~1.5dB
- HI FREQ:100
僕はこんな設定にしてます。
最初にも言ったように
3段目は
やったりやらなかったりします。
- メロでメロメロしすぎ
- サビでサビサビしすぎ
つまり
メロとサビで
音量差があまりにもデカすぎる場合とかに
- ダメ押し
的な意味合いで使います。
また、
3段目の設定のコンプレッサーを
1段目に持ってきて、
あらかじめ
メロメロ部分と
サビサビ部分をグッとならしてから
本来の1、2段目をかけ始める…
とかってパターンもあります。
色々試してみてください。
メロとサビを別トラックで編集するのもいい
これ言うと本末転倒ですが、
たとえばメロとサビの音量差が
あまりにもデカすぎる場合は
『別トラックで編集』
したほうが
スマートに決まることもあります。
(分けた場合でもそれぞれに多段がけはするが)
僕はDAW『REAPER』使ってるんですけど
空間系トラックから
いくつものトラックに
センド飛ばすの手間なので、
なるべく1トラック内で完結させようとしてます。(訳:横着)
あと、
PCのCPUを節約する意図もあります。
アナログモデリングの
わりと重めのコンプを何個も使うと
すぐに動作がカクカクするので…
PCスペック低い人にとっても
コンプレッサー多段がけ×1トラック完結
は有効な手段でしょう~
なぜ多段がけするのか?
「ごちゃごちゃやらんでオートメーション書けばいいじゃん」
「Waves『Vocal Rider』使えばいいじゃん」
という声がたくさん聞こえてきました(幻聴)
ヤダ、書きたくない。
Vocal Rider重い。
PS.
ここまでやっとくと
オートメーション書く手間が最低限で済みます。
じっさい、僕はいつも
特に小さい1音ずつ、とかしか
オートメーション書きません。
ガチメンドクセーからよぉ!
だし、
面倒事をショートカットして
時短できるということは
- コンテンツ制作速度が上がる
- 高スパンで歌ってみた動画をリリースできる
→伸びるチャンスを増やせる
好循環を生み出せます。
ご参考までに~
→今回紹介した3つのコンプレッサーが一気に手に入るオトクなバンドル
もう埋まってたらすいません↓
歴10年が歌ってみたMIX承ります 1000再生に届かない悩みを一緒に解決しましょう!