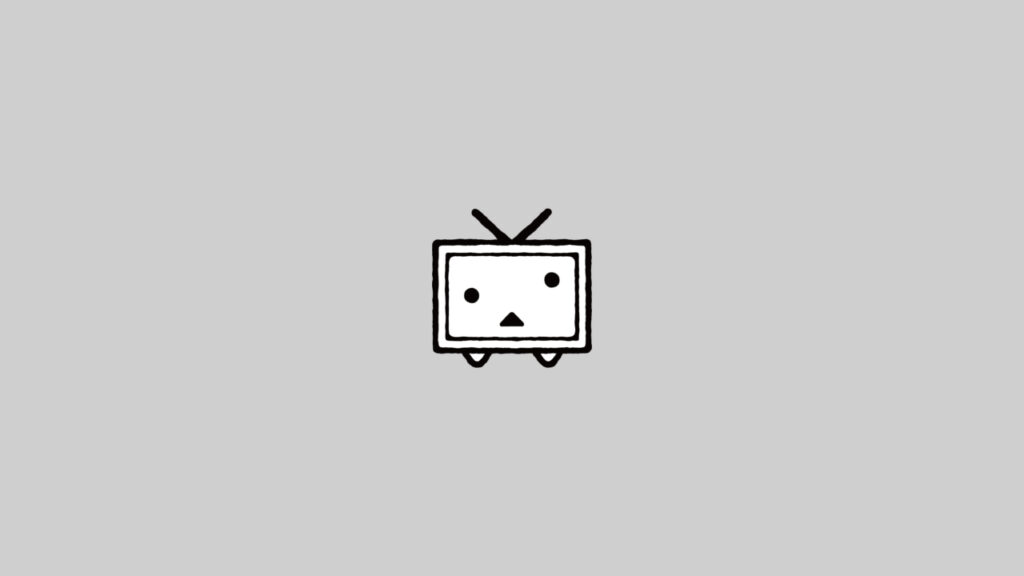MIXは何となくやれるけど、
マスタリングに入った途端に手が止まる。
EQ、コンプ、リミッター…
触ってみるけど、
「これでいいのか?」
ってずっと不安。
そんな声をよく耳にします。
マスタリングって特に
人によって
言ってることがまるで違うから
正解が見えにくい世界なんですよね。
そのせいで
「やればやるほど音が悪くなる…」
なんて
逆転現象に陥ることもしばしば。
でもそれ実は
あなたのセンスや努力が
足りないわけじゃないんすよね。
『判断基準があいまいなまま進めてる』
ことが原因だったりします。
【大前提】マスタリングは”最終微調整”でしかない
MIX段階での不備を
マスタリングでなんとかねじ曲げて
修正しようとしてませんか?
- マスタリングってなんかすごい
- 全部どうにかしてくれる最終兵器
みたいな印象、持ってませんか?
残念ながらマスタリングって
万能じゃありません。
全知全能じゃありません。
むしろ、
いちばん融通が効かない工程
と思っておいたほうがいい。
マスタリングって
料理で言えば
”味付けの最終微調整”なんですね。
たとえば、
薄味のスープを
「もうちょっと塩気がほしいな」
と思って調整する。
これがマスタリングです。
これが、もしも最初から
ケチャップどばどばの
濃い味付けになってたら?
「やっぱあっさり系がよかったな…」
と思っても、
あとから薄味には戻せませんよね。
その料理、最初から作り直す必要があります。
同じく、
MIX段階で
- 音が潰れてたり
- バランスが崩れてたり
- 音像が偏ってたり
ソースがそんな状態だと、
マスタリングの段階では
どうにもならないことが多い。
それを無理に
EQやコンプで
修正しようとすればするほど、
かえって音が濁っていったり、
不自然になっていったりします。
マスタリングでできること・できないこと
- 全体のトーンの微調整
- 音圧の統一
- 曲間の整備
- リリースフォーマットへの最適化
- バランスが悪いMIXの再構築
- 個別の音の定位の修正
- 崩れたリズムの補正
- 消し去りたい楽器・声・ノイズのカット
マスタリングって、
全体を整える仕事であって、
部分的に治していく作業じゃない。
- 出てほしくないキックが暴れてる
- ボーカルが引っ込んでる
とかいう問題を、
2mix状態になってから
何とかしようとするのは、
出荷直前の弁当に詰められた
真っ黒に焦げた唐揚げを、
パッケージの上から美味しくする…
そんくらい、無茶。

↑さぁ、美味しく食べられる状態に戻してください!
僕にはムリです…
マスタリングで一番大事なのは
『MIXが仕上がっていること』
なんですよね。
それができてない状態で
マスタリングに突入しても、
- EQで苦しんで
- コンプで迷って
- リミッターで潰して
結果、よく分からない音が
出来上がるだけです。
まずはこれを
サクッと参考にしておくといいですよ↓

マスタリングでよくある失敗例・原因
マスタリングが
”最終微調整”にすぎないと
頭では分かってても、
いざ作業に入ると
- つい余計なことをしてしまったり
- やるべきことじゃなく、やりたいことをしてしまったり
- 逆に何をすればいいか分からなくなったり
迷子になることもあるでしょう。
特に、
歌ってみたなど
個人制作者の場合。
自分でマスタリングまで
完結させようとしたとき
”判断基準のなさ”が一番の敵になります。
ので、
マスタリングでつまずきやすい
具体的な失敗パターンを
いくつかピックアップして紹介します。
「これ、やっちゃってたな…」
と思うものがあれば
ぜひ次の作品で意識してみてください~
リファレンストラックを使用していない
ぶっちゃけ
マスタリングの失敗原因は
ここが9割って言ってもいいくらい。
特に、歌ってみたとか
インディーズの楽曲でよく見られますが、
『そもそもプロの音源をしっかり聴いてない』
ていうケースが非常に多い。
どうなっていれば正解の音なのか?
いまいち認識できてないまま
がむしゃらに突っ走ってしまう。
ゴールのないマラソン状態。
そもそも、
リファレンストラックって
プロがMIXもマスタリングも済ませた
”完成形の音源”なわけです。
答えがすぐそこにある状態ですから、
まずは自分の音源と
対象の音源を並べて、
ちゃんと聴き比べてみましょう。
- 低域の量感
- 中域の明瞭さ
- 高域の抜け
- ステレオの広がり
- 音圧の感じ方
- 音の立体感や空気感
聴き比べれば
「自分の音のどこが違うのか?」
はっきり見えてきます。
もしも
「ぜんぜん違うじゃん…」
と感じたとしたら。
おめでとうございます。
大ヒントにたどりつけましたね。
ちゃんと聴けば、
近づけるべき場所が
ちゃんと分かるわけです。
「何かよくわからないけど満足できない」
という状態から、
「ここの音圧が足りない」
「この帯域がこもってる」
といった
具体的な課題が見えてきます。
そこに向かって処理をしていけば、
自然と仕上がりのクオリティも
上がっていきます。
もちろん、
リファレンスと
全く同じ音にしろってわけじゃありません。
曲のジャンルや方向性によって
必要な処理は変わります。
ですが
”耳のものさし”を持つための基準として
リファレンスは必須です。
だって
①わからないから
②今、できてない
んですから。
なので、ぜひともですね、
『まず参考音源を並べて聴く』
ことを、ルーティン化してみてください。
たったこれだけでも
判断力の精度は格段に上がります。
フェーダーで解決できる問題をプラグインで無理やり処理している
ハイテクなソフトを
いじいじしたくなる気持ち、
すごくよく分かります。
最新のプラグインを買ったら
とにかく使いたくなる。
あれこれ試して、効果を実感したくなる。
これはもう…ねぇ!?
人間として自然な感情でしょう。
でも忘れちゃいけないのは
『プラグインの設定って→必須じゃなくて“任意”の作業』
だということ。
たとえば、
新しく買った調味料を
「せっかく買ったから」という理由で
ぜんぶの料理に入れてたら、
当たり前ですが
味はぐちゃぐちゃになりますよね。
「なんでこの料理にこれ入れたの!?」
「入れたかったから……」
そんなん理由になるかーーー!!!
音作りもまったく同じ。
ただボリュームを
下げれば済む話なのに、
EQで削ったり
コンプで潰したりしてしまう。
その結果、
元の音が持っていた魅力や自然さを
失ってしまうことってよくあります。
ボーカルがちょっと大きいだけなら
フェーダーをちょっと下げれば済む話。
なのにわざわざ、マスタートラックで
- マルチバンドコンプで潰して
- EQで削って
- リミッターで締めて…
なんてやってしまうと、一発で音が死にます。
たまごスープを作るのに
「入れたいから」という理由で
”コーヒー”なんて入れたら
一発で台無しじゃないすか?
完全に自己都合、エゴじゃないすか?
ので、
- 本当に必要な処理なのか?
- それともただ“使いたいだけ”なのか?
作業中の自分に
投げかけてみてください。
シンプルな解決方法があるなら
まずはそっちを使う。
プラグインは
どうしても必要なときだけ登場してもらう。
- 必要ないなら足さない
- 必要ないなら引かない
そんな潔さが
あなたの音のクオリティを
底上げしてくれます。
デジタルクリッピングを起こしている
これ、意外と
聞き分けられない人が多いんですよね。
「音が割れてる」
「バリってる」
とかとか…
言葉では分かってるはずなんだけど、
実際の音の中で
じゃあどこからがクリッピングなのか?
を聴き分けるのって、案外むずかしい。
しかも厄介なのは
単なるクリッピングだけじゃなくて、
似たような破綻の仕方が無数にあること。
- コンプやリミッターによる不自然なポンピング
- ピークを潰しすぎて平坦になった音像
- アタックが死んで、ダイナミクスが失われた音
こういった、
”失敗とまでは言えないけど違和感のある仕上がり”
に気づけないまま、
「これでOKかな…」と
判断してしまうケースがめちゃくちゃ多い。
つまり何が起きてるか?というと、
『いちばん”ちょうどいい部分”を知らないから、そこに辿り着けない』
てことなんですね。
まぁ、
これは感覚の問題でもあるし
経験の問題でもある。
実際のところ
「これがちょうどいいんだな」
ていう音を何度も聴いて
体に染み込ませるしかないんですよね。
ちょっと攻めすぎたな、と思ったら1歩引く。
限界まで音圧を上げる前に
いちどリファレンスに戻ってみる。
そういう
冷静さと客観性がないと、
知らないうちに音が壊れていくのが
マスタリングの怖いところですね~
音圧を上げたい気持ちは分かります。
でも、潰れてしまった音に
あなたのリスナーは感動しません。
「割れてないからセーフ」
じゃなくて、
ちょうどよく張ってる
ギリギリで気持ちいい
清々しい聴後感がある
を目指してみてください。
その一歩手前で止める勇気こそ
プロの仕事です。
プロは寸止めがウマイって~こと(???)
リスニングテストを限られた環境だけでしかしていない
- お気に入りのイヤホン
- いつものヘッドホン
『でしか』確認してない人、
けっこう多いんじゃないでしょうか。
たしかに、
慣れてる環境って安心感がありますし、
聴き慣れてるからこそ
細部まで気づけるってメリットもあります。
でも、そこだけで判断してしまうのは危険。
なぜなら、
僕らが丹精込めて作った音源、
実際に聴いてくれるリスナーは
驚くほど粗末な環境で聴いている
ことがほとんどだからです。
- スマホのスピーカー
- ノートPCの内蔵スピーカー
- 1000円のBluetoothイヤホン
- 音質の悪いカーステレオ
- ザラついた街中の環境音と一緒に…
そういう悪条件の中でも
成立する音のほうがよくないですか?
あるスタジオでは
最終確認を”ラジカセ”で行うという話を
聞いたことがあります。
なんでそんなローファイな機材で?
と思うかもしれませんが、理由は一緒。
『リスナーの環境に合わせるため』
なんですよね。
個人で試せる範囲でも工夫できます。
- いつもの3万円のイヤホン
- いつもの3万円のヘッドホン
- コンビニで買える3000円のイヤホン
- ノーブランドの1000円のイヤホン
- スマホ本体のスピーカー
- ノートPCのスピーカー
- カーステレオ
予算が限られてても
ちょっと視点を変えるだけで
判断精度はグッと上がります。
たった数分でいいので
『いつもと違う環境』でのチェック、
ぜひやってみてください。
モニタースピーカー・ヘッドホンの音が信用できない(色付けが強い)
これは僕自身、
DAWを触りはじめたばかりの頃に
やってたミスなんですが…
- モニター用の機材
- リスニング用の機材
これの違いが
全然わかってなかったんですよね。
見た目がいかつくて
作りも堅牢だからってだけで
「これはいいヘッドホンである!」
ていう、
なんとも解像度の低い解釈をしてましたw
リスニング用の機材って
基本的には
『気持ちよく聴こえるように”味付け”されてる』
んですよね。
低音がちょっと持ち上がってたり、
高域がキラッと明るめに調整されてたり。
で、
その”味付け済みの音”を聴きながら
MIXやマスタリングをしてしまうと、
さらにその上にから
”別の味付け”をしてしまうことになります。
料理で言うところの
すでに甘辛く味付けされた食材に
「ちょっと物足りないな」と思って
さらに甘辛タレをぶっかけるようなもの。
リスニング用機材=味覚障害(音源編集において、ね?)
みたいなもので、
つまり、正確な味が判断できないわけで。
結果、
クセが強すぎる仕上がりになって、
リスナーからすると
「なんか聴きづらい…」て印象になる。
つまり、
色付けの強い機材で音を作ると
最終的に
”万人にとって心地いい音”から
遠ざかっていくんですよね。
せっかくの音源なのに
特定の環境でしか気持ちよく聴こえない=再生環境を選ぶ
状態になってしまう。
ので、やっぱり、
『音を作る工程においては、できるだけフラットな機材を使う』
というのが基本。
モニター用スピーカーや
モニター用ヘッドホンを使って
何も足されてない
素の音を聴きながら処理する。
これが
あらゆる環境で破綻しない音作りに
最も近く、コスパがいい環境です。
よっぽどの玄人の人は
違うこと言うかもですけど、
僕が実際に上達した要因でもあるので
この意見を推させていただきます。
もちろん
リスニング用での
最終確認も必要ですが、
- 編集はモニター用機材ベースで
- 確認はリスニング用機材と並行して
というシーンの使い分けができると
仕上がりがグッと安定しますよ。
モニターボリュームが大きすぎて客観的に判断できていない
これもね、僕自身
いまだにやっちゃいがちなんですが…
「自分が気持ちいいと思う環境から抜け出せない問題』
ないですか?
音量を上げると
音の迫力も増すし、
ベースの太さとか、
高域のきらびやかさとか、
妙にいい感じに聴こえてきますよね。
で、それを
「自分が作った音である」
と錯覚してしまう。
実際、
「音量を上げると音がよく聴こえる」てのは
音響心理学的にも立証されてる現象です。
あと、僕的には、
これは単なる
習慣の問題じゃなくて、
たぶん
”心理的なブロック”も
関係してる行動だと思ってます。
- 面倒な作業をさっさと終わらせたい
- 次の修正点に気づきたくない
- 今の自分の作業を「よくできてる」て思いたい
そういう
無意識の逃避反応みたいなものが
音量MAXにつながってること、
実はけっこうあると思うんです。
でも本当に
精度の高い判断をしたいなら、
『でかい音・小さい音、どっちでも聴く』
てのがセオリーです。
特に、小さい音にしたとき。
これめちゃくちゃ重要で、
試しに音量を下げてみると
致命的なボロが浮いてくるんですよ。
『音量を下げたときにしか見つからない致命傷』
とも言える。
たとえば
- ボーカルが埋もれる
- キックの存在感が消える
- トラック全体がモコモコする
- バランスが崩れる
大きな音で
ごまかされてた部分が浮き彫りになります。
試しに…
ボリュームフェーダーを
思い切って絞ってみてほしい。
で、聴き直してみてください。
たぶん、絶望しますw
でも、それでいいんです。
”気持ちいい”は、作業者のゴールではない。
それは『リスナーに感じさせるべき要素』です。
ワイらだけ気持ちよくなってどうすんネン!
て話よ。
まずは、
”冷静な音量”で判断する習慣を
少しずつ取り入れてみてください。
すると
自分のマスタリングの
クセや弱点に
もっと早く気づけるようになりますよ。
原曲の魅力を理解していない(意図を把握できていない)
あとね、メンタル。
マスタリングが
うまくいかない人の中には、
そもそも
『何も聴けてない』
状態のまま作業してるケース
てのもあります。
たとえば
- MIXという作業に夢中
- マスタリングという作業に夢中
- アップロードして、再生数やいいねの反応でアドレナリン出すことに夢中
つまり、
”テイカー(奪う側)”のまま
作業してしまってる状態。
こうなると、
いちばん大事なことである
「この曲の魅力って何だったっけ?」
という視点が
まるっと抜け落ちてしまうんですよね。
- ボーカルの繊細なニュアンスだったり
- アレンジの意図だったり
- リリックに込められた温度感だったり
それらを感じ取らないまま
処理を加えると、
曲の輪郭がどんどんぼやけていくんです。
特に
歌ってみたの場合なんかは、
”すでに完成された原曲”という
明確な基準があるわけです。
これはめちゃくちゃありがたいことで、
プロが作った最高の設計図が
手元にある状態。
それなのに
「とにかく自分の音にしたい」
「もっと派手に仕上げたい」
とかいう理由で、
原曲の空気感や意図を
無視してしまうのは
さすがに本末転倒です。
いや、別に、
「原曲こそ神!改変などあってはならない!」
なんて極端なこと言う必要はありません。
ただ、
最低限のリスペクトとして
『原曲をちゃんと聴く』
ことくらいはしてほしいんです。
その上で
「ここが原曲と違うのは、こういう理由」
「このアプローチの方が自分の声に合うと思った」
ていう
”自分なりの再定義”が乗れば、
作業プロセス後段である
マスタリングの方向性にも
自然と一貫性が出てきます。
音を整える前に”何を活かすべきか?”見抜く力。
これがマスタリングにおいて
重要な基礎体力だったりします。
耳が疲れた状態で作業している(労働限界)
極めつけがこれです。
物理的な限界。
みんな、めちゃくちゃ頑張ってます。
夜中まで作業したり、
何時間もリファレンスとにらめっこしたり。
少しでもいい音にしたいって
必死に試行錯誤してる。
でもねぇ~~~
頑張って頑張って、
頑張った末に、
そもそも”耳が機能してない状態”で
迷走してしまっては元も子もない。
もう少し、冷静に考えてみてください。
疲れた目で色調整しても、正しい色は見えない。
疲れた手で絵を描いても、線は歪む。
疲れた脳で仕事しても、ミスが増える。
音もまったく同じ。
耳が麻痺した状態で
正解に辿り着けるわけがないんですよ。
じゃあ解決策は何か?
めちゃくちゃシンプル。
『寝る』
耳が回復するまで
PCから離れて、
一回リセットしてください。
「いや、そんな悠長なこと言ってられない」
ていう気持ち、すごく分かります。
早くリリースしたい気持ちは分かります。
リスナーが待ってる焦り、分かります。
早く稼がないと…分かります。
早くチヤホヤされたい…分かります。
でも冷静に考えると、
あなたのその欲しい結果に
近づくために必要なのって、
『最高のソリューションと、それの提供』
なわけじゃないですか?
じゃあ
何よりも先にやるべきなのは
『体調管理』なのでは?
そう思えてなりません。
クオリティの高いマスタリングは
根性からは生まれません。
”回復した耳”からしか生まれません。
疲れたまま
無理して作ってしまった音源は、
公開後に
「あれ、なんか違ったな…」
て、自分で気づくハメになります。
そんなの
めちゃくちゃ悔しいじゃないすか。
だから、
焦ってる時こそ、DAWを閉じてみる。
それができる人が、
最高に良い音を
作れるんだと思いますよ。
「今日はもう寝よう」
そうやって一晩置いたあと、
音を聴き直してみてください。
きっといろんなものが
クリアに見えてくるはずです。
結局は『楽しんだもん勝ち』
実はここまで、
マスタリングでありがちな失敗を
- 機能
- 環境
- 概念
3つの切り口から紹介してきました。
- 機能面…判断ミスや過剰な処理のリスク
- 環境面…再生条件やモニター精度の大切さ
- 概念面…原曲への理解や自分の体調管理の重要性
音そのものでもあり、さらに
”それを触る自分の状態”も
音に影響するってことでしたね。
で。
結局のところ一番大事なのは
『あなた自身が楽しめてるかどうか』
なんです。
マスタリングって、
正直ちょっと地味でしんどい作業です。
理屈も多いし、
やればやるほど沼ることもあるし、
終わりが見えないこともある。
だから逆に、
その過程を楽しめる感覚を
今後、忘れないようにしてほしいんです。
「おっ、ちょっとプロっぽくなったかも」
「あれ、意外と良くなってきてる?」
「この帯域触るとめっちゃ変わるなー!」
変化を面白がれることが
音を磨くエネルギーになる。
”楽しさ”って、必ずしも
いつも完璧な環境とか、
高価なプラグインとか、
特別な才能とか、
そういう分かりやすいモノから
くるものとは限らなくて、
ちょっとした気づきとか
自分の成長に気づけた瞬間から
生まれることもあるんですよね~
それがあるだけで
何時間でも没頭できるし、
毎回ちょっとずつ音が良くなっていく。
労働を労働と思わない状態。
それってもう勝ちでしょw
マスタリングの技術も、
判断基準も、
時間をかければ自然と身についていきます。
焦らず
自分のペースで
”遊びながら上達していく”
くらいの気持ちでいい。
音楽は本来、
楽しむためにあるものですからね。
楽しみながら作った音は、
ちゃんとその空気がリスナーに届きます。
だから今日も
自分の耳と気持ちに正直になって、
いい音を、気持ちよく育てていきましょう。
こんな記事もおすすめ↓